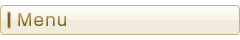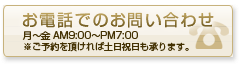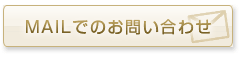主な遺言の形式には、次のものがあります。
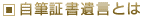
遺言書の全文、日付および氏名を自筆し、これに押印することによって作成します。もっとも簡単ですが、方式を満たさないと無効になるので注意を要します。
なお、相続が開始した後、家庭裁判所で封を開け、検認という作業が必要になります。封印のある遺言書を勝手に開けてはいけません。

公証人によって、作成されますが、以下の要件を満たす必要があります。
・証人2人以上の立会いがあること
・公証人に対する遺言者の口授があること
・公証人の筆記および読み聞かせまたは閲覧があること
・遺言者および証人の署名・押印があること
・公証人の付記・署名があること
公正証書遺言の場合は、検認は必要ありません。
証人は、公証役場に頼めば、用意してくれます。
一番、確実な遺言の方式ですが、公証人に支払う報酬が発生します。

以下の方式を満たす必要があります。
・遺言者が遺言書に署名・押印すること(この方式の遺言書は、自筆でなくてもいいです。)
・遺言者が遺言書を封入し、証書に用いた印章で封印すること
・公証人1人および証人2人以上の立会いをもって秘密証書遺言である旨および遺言の筆者の氏名・住所を申述すること
・公証人が日付および遺言者の申述を封紙に記入し、遺言者、証人、公証人が封紙に署名し、押印すること
この方式の場合、家庭裁判所での検認が必要となります。

いずれの方式の遺言書であっても、後から書き換えた遺言書が有効になります。
つまり、いつでも遺言の内容を書き換えることができます。
特定の相続人の相続分とゼロとする遺言も可能ですが、遺留分権利者の場合、遺留分減殺請求をして、裁判で争うことになってしまうこともあり得るので、少なくとも遺留分は相続させた方がいいと思われます。
所長ブログ